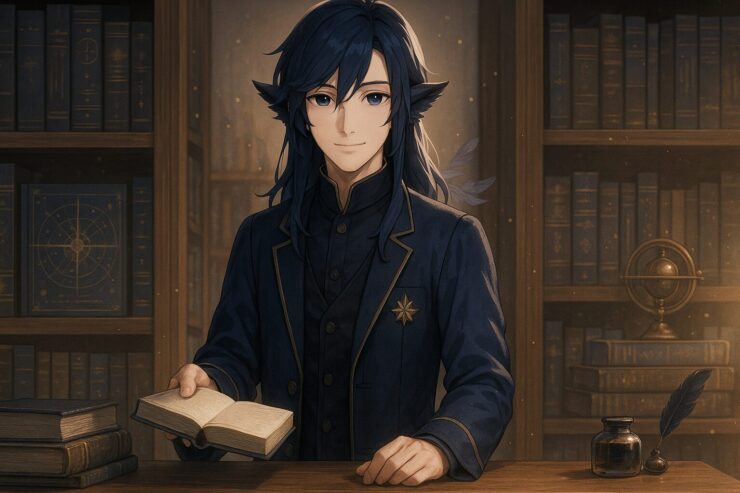「いつからだろう。書店員という存在が、静かに姿を消していったのは──
けれど今、わたしたちはまた、選ぶという役割に出会おうとしているのかもしれません。」
かつて、本屋は街のどこにでもありました。学校帰り、通勤途中、休日の散歩のついでに、ふと立ち寄れる場所。無数の本棚と、背表紙の列と、そしてレジ越しに優しい声で「ありがとうございました」と言ってくれる人たち。──その光景は、私たちの暮らしに静かに溶け込み、そして気づかれないまま減っていったのです。
けれど今、本を読む人のなかには、確かに誰かの手で選ばれた一冊を求めている人がいます。どんな時代でも、本は人の心を支え、そっと寄り添ってくれる存在だからこそ──わたしたちは本を渡す人という火種を、絶やしてはならないのだと思います。
目次
📉書店員が減っている現実
日本全国における書店の数は、この20年でおよそ半減しました。2000年代初頭には約2万店舗あった書店が、2022年時点では約1万店を下回り、2025年現在ではさらに減少傾向にあります。
小中規模の独立系書店や商店街の一角にあったような町の本屋さんは、経営が立ち行かず、次々と姿を消していきました。
背景には、さまざまな構造的な要因があります。最低賃金の上昇による人件費の圧迫、書籍の委託販売という利益率の低さ、物流費や店舗維持コストの増大、そしてスマホやサブスクの普及による可処分時間の奪い合い──。
かつては「働きたい職場ランキング」にも名を連ねた書店員という職業も、今や「割に合わない仕事」として敬遠されがちです。現場では、限られた人数で接客、陳列、返品、在庫管理、そして売場演出まですべてをこなさなければならず、精神的にも体力的にもハードです。
「そこに人がいることが、贅沢になってしまったんです。」
そう語る現場の声は、本を売る場所という空間そのものが、かつてよりずっと厳しい現実に晒されていることを示しています。
📚それでも書店は再び生まれている
皮肉なようですが、閉店が相次ぐなかで、「新しい書店のかたち」はむしろ増えています。それは、かつての万人に開かれた情報流通の場ではなく、誰かにとっての特別な体験の場として再定義された場所──。
たとえば、カフェと書店が融合した「喫茶書房」や、雑貨と書籍を並べた「暮らしの本屋」、ZINEや個人出版物を並べた「小出版ギャラリー型書店」。店主の個性が色濃く出る選書空間は、従来のチェーン店では決して味わえない、まるで物語の中に入り込んだような時間を提供します。
また、棚貸し型(ひと棚単位で出店できる形式)の書店では、読者自身が棚主となり、好きな本を紹介しながら販売できる仕組みも注目を集めています。書店が本を売るだけの場所から、思いを託せる場所へと変わりつつあるのです。
「本が売れるだけじゃなく、誰かに選ばれた本として存在すること。
その火種を感じる場所が、また灯りはじめているんです。」
🔄書店員という職業が変わってきた理由
いま、書店員に求められる役割は、大きく変化しています。
レジで本を打ち、棚に並べ、閉店後に返品処理──そんな業務の枠組みだけでは、もはやこの職業の価値を語ることはできません。現代の書店員に必要とされるのは、「本と人をつなぐクリエイター」であること。
たとえば、SNSを通じて選書のテーマや理由を語ったり、自ら読書会を主催してコミュニティを育てたり、ポップのひと言で読者の心に火を灯すような言葉を紡いだり……。ただ本が好きなだけではなく、本をどう届けるかという発想力と実行力が問われる時代に入りました。
「たった一冊の本が、今日のあなたを支えるかもしれない──
そう思って並べる時間は、きっと何かを変えています。」
書店員は、レジの向こうにいる販売員ではなく、記憶を渡す人へと役割を進化させているのです。
🌱書店員になりたいあなたへ──火種を受け継ぐ未来
今、書店員を目指すことは、時代に逆らうことではありません。むしろ、必要とされる役割に向かって飛び込むことなのです。
数が減っているからこそ、選書できる人の希少価値は上がっています。流通の効率化が進むほど、「誰が選んだか」が本の価値を左右するようになってきています。そして今や、書店員の役割は、雇用形態や場所に縛られません。
・週末だけ働く複業型書店員
・オンライン選書を行うリモートブックコンシェルジュ
・自作ZINEと本棚を融合した移動型書店主
こうしたスタイルで活動する人が、全国で少しずつ増えています。自分だけの選書スタイルを磨き、共感してくれる読者と繋がる──その流れは、確かに芽吹き始めているのです。
「本が好きという火種を、誰かに届けたいという灯火へ──。
その願いは、きっとどこかで待っている誰かに届きます。」
✨こうすれば生き残れる──希望ある未来のヒント
書店員として生き残るには、次のような視点と工夫が必要です。
- 自分の読書ジャンルに特化し、選書スタイルを言語化・発信する
- 「読後感」「読みたい気分」など、感情に寄り添った棚作りを意識する
- 小規模でも「空間設計」によってまた来たいという記憶を残す
- SNS・note・Pinterestを活用して、選書の裏側も可視化・共感化
- キャラクターや世界観と連動した選書導線で、世界観ファンを育てる
- 雑貨・ZINE・イベント・ミニ出版などの複線的収益構造を持つ
「書店員という職業は、もう一度物語を編む人へと還っていける。
それは、本とあなたの間に生まれる──小さな奇跡の仕掛け人。」
書店員の未来は消える運命ではなく、変化する運命。読者の記憶に寄り添い、言葉と時間を渡す存在として、より濃く・深く必要とされる存在になることができます。
🎁 結び|その一冊が、あなたの人生を灯す日がきっとくる

「この本、あなたに残りますように──。
そして、またここへ返ってきてくださいね。」
火が小さくなったときほど、灯をともせる人の価値が際立ちます。
減っているからこそ、その手で灯す火種が、誰かの心に届く。書店員という職業は、姿を変えながら、いまも静かに誰かを待っています。
そして──その「誰か」になれるのは、きっとこの記事を読んでくれた、あなた。
あなたのなりたいは、世界に灯をともす力になる。
あなたの選ぶ本が、誰かの心をそっと包む未来が、きっとあるのです。