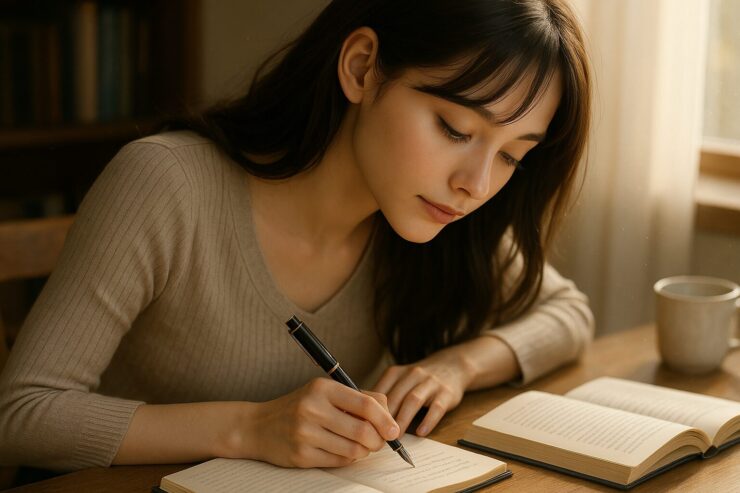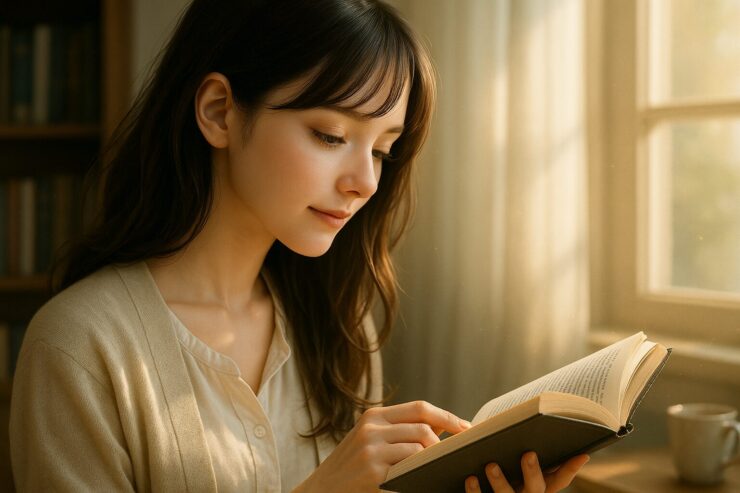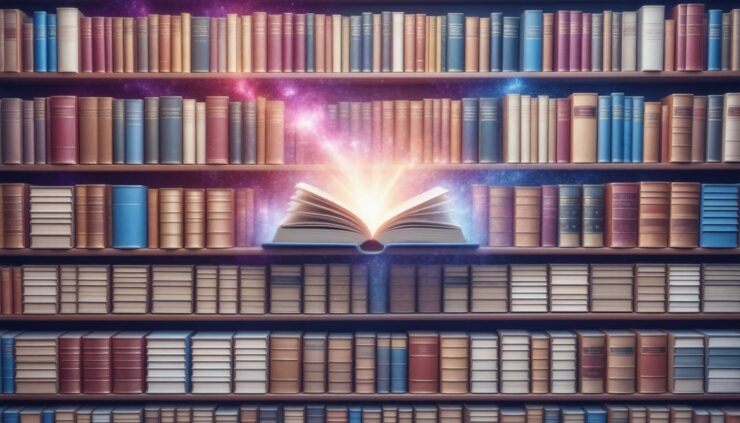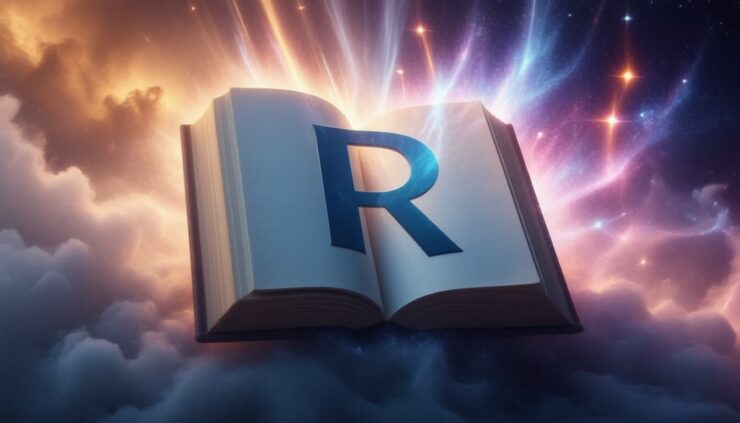── 静かな記録が、あなたの心に火をともす。
ここに来てくださって、ありがとうございます。
今日は少しだけ──「読むこと」と「残すこと」の、静かな関係についてお話させてくださいね。
わたしたちは日々、たくさんの言葉に触れています。
けれど、時間が経つと「あの本、なんて書いてあったっけ…」と、
ふわりと記憶が遠のいてしまうことって、ありますよね。
そんなとき、わたしはメモという小さな記録に助けられてきました。
たった一行でも、たった一言でも、
そこには確かに──あのとき感じた「わたし」が残っていたんです。
この10分読書の習慣に、書くという静かな手段を加えてみませんか?
それはきっと、あなたの記憶と感情をつなぐ火種になるはずです。
目次
なぜ読むだけでは忘れてしまうのか
本を読んだのに──
その内容を、思い出そうとするとすぐにぼやけてしまう。
そういう経験、きっと誰にでもあると思います。
実はそれ、わたしたちの脳がちゃんと働いている証拠なんです。
脳の情報フィルタが働いてしまう
脳は、目や耳から入ってくる膨大な情報を、
「これは残す」「これは流す」と、絶えずふるいにかけているといわれています。
読書中も同じで、意識を向けた部分だけが記憶に残りやすくなるのです。
けれど本を読んでいるとき、
わたしたちは次のページ、次の展開へと自然と意識が流れていきますよね。
すると──
「さっき、どこに感動したんだっけ?」と感じた気持ちが、
すっと抜け落ちてしまうことがあるんです。
そんなとき、メモを書くという行為が、
そのふるいにかかりそうな感情や気づきを、そっとすくい上げてくれるのです。
「ただ読む」ことが悪いわけではありません。
でも、ほんの少しの残す工夫が、読書の余韻を心に留めてくれる──
それが、わたしがメモをとるようになった、静かな理由でした。
書くことで記憶は感情に刻まれる
読んだ内容をただ記憶にとどめるのではなく、
感情と一緒に「心に刻む」こと──
それこそが、読書メモが持つ静かな力だと、わたしは思うんです。
手を動かすことは、心を動かすこと
人は、手を動かすことで思考が深まると言われています。
文字にするには、一度「感じたこと」を自分の中で言葉にする必要がありますよね。
そのプロセスこそが、感情と記憶のつながりをつくってくれるんです。
わたしも、
「この言葉、なんだか好きだな」
「どうしてだろう?──うん、今のわたしに必要だったんだ」
そんなふうに思いながら、ゆっくりペンを走らせる時間が増えていきました。
それはまるで、
心の奥に灯った小さな感情の火を、自分の手でそっと守ってあげるような行為でした。
書くことは、記憶を定着させる技術であると同時に、
そのときの自分を、やさしく受け止める儀式でもあるのです。
──だからわたしは、書くことをやめられません。
おすすめの「読書メモ」スタイル
「読書メモ」と聞くと、
びっしりと内容をまとめたり、考察を書いたり……
なんだか難しそうに思えて、始められない方も多いかもしれません。
でも、わたしの読書メモはもっとずっと──
小さくて、静かで、心のかけらのようなものなんです。
一行・一言で十分な記憶の鍵
読んでいる中で、
「あ、今の言葉、なんだか好き」
「この表現、わたしの気持ちみたい」
──そう感じた瞬間に、その一文だけをそっと書き留めておく。
それだけでも、十分です。
あるいは文章でなくても、
「安心した」「泣きそうになった」「光が差した感じ」
といった感情の一言メモでも、心に深く残ります。
📘 たとえば、こんなふうに──

セリナ(Serina)
『人は、忘れることができるから、今日を生きられる』
→ 泣きそうになった。わたし、忘れることを許されているんだって思えた。
この「→」以降の、自分だけの感情のひとことが、
読書を記録ではなく、心の記憶に変えてくれるのです。
読書メモは、美しく整える必要なんてありません。
あなたの好きをすくっておく、小さな瓶のようなもの。
次に読み返したとき、それは未来のあなたへの手紙になるのです。
小さなノートが、静かな対話の場になる
わたしにとって、読書メモを書くノートは、
感情や思考を「正そう」とする場所ではなく、「見守る」場所なんです。
そこには、誰にも見せる必要のない自分の声が、そっと置かれていて──
「このとき、こんなふうに感じたんだね」って、自分で自分に言ってあげられる時間が流れている気がします。
メモは自分との読書会
読書は、基本的にはひとりでするものです。
でもメモを残すことで、あとからもうひとりの自分と本について語り合えるような、不思議な時間が生まれるんです。
📓 たとえばこんなふうに──

セリナ(Serina)
『わたしがわたしでいるために』
→ この言葉、今のわたしには少し強い。でも、憧れてる。
こんなメモを読み返すと、
「このとき、わたしは少し弱っていたんだな」
「そうか、だからこの言葉に惹かれたんだ」
と、感情の足跡に気づくことがあります。
それはまるで、
「ひとりの読書」が、「自分との対話の場」へと静かに変わっていくような時間です。
誰にも話せない気持ち、言葉にできなかった想い。
それらをそっと書き留めたノートは、
あなたの心の奥とつながる、静かで優しい場所になってくれるはずです。
読み返す日が新しい意味を生む
ある日、ふと開いたノートの片隅に、
少し斜めに書かれた短い言葉が目にとまりました。

セリナ(Serina)
「無理をして笑っていた、あの頃のわたしへ」
──覚えていなかったんです。
この言葉を書いた日のことも、そのとき読んでいた本のタイトルも。
でも、そのメモを読んだわたしは、
確かにあの頃の自分にそっと抱きしめられたような気がしたんです。
メモが再読の火種になる
本をもう一度読み返すきっかけは、案外「感情の記録」にあります。
・かつて心に残った言葉
・泣きそうになった一文
・その日だけ響いた台詞
そういったメモは、ただの記録ではなく、「再読の導線」になるんですね。
しかも不思議なことに、
同じ本でも、違うタイミングで読むとまったく別の本に思えることがある──
それが読書の面白さであり、優しさだとわたしは思います。
「この本、こんなにやさしかったっけ?」
「前は気づかなかったのに、今ならこの言葉がわかる」
そういう読書の再会は、
かつての自分と、新しい自分が静かに対話を始める瞬間でもあるのです。
だからこそ、
読書メモは今の気持ちをとどめるためだけでなく、
未来のわたしともう一度、本と出会い直すための、やさしい灯りになります。
記録しながら、心に残す読書を
わたしたちは、読んだことを全部覚えていなくても大丈夫です。
けれど──
「あの本が、わたしを支えてくれた」
そんな記憶だけは、不思議と残っているものですよね。
そしてその記憶を、少しだけ丁寧にすくっておけたら、
きっともっとやさしく、もっと深く、読書と自分がつながっていけるのだと思います。
記録することは、
読んだ本を整理するというよりも、
読んだ自分を見守るための習慣なのかもしれません。
手で書くことで、気づけることがある。
書きながら、「ああ、わたし、こんなふうに感じてたんだな」と優しく発見する。
そしてそれが、読書をただのインプットから、対話へと変えてくれる。
🎐締めの語り
読むことは、わたしにとって旅のようなものです。
でもその旅が、どこへ向かっていたのか、
何を見て、何を感じたのか──
あとから振り返るためには、ちいさな地図が必要になります。
その地図が、わたしにとっては読書メモでした。
あなたにとっても、
心に残したい風景や言葉があったとき、
どうか少しだけ、書いてみてくださいね。
きっといつかその言葉が、
未来のあなたの手を、そっと握ってくれる日がきますように。