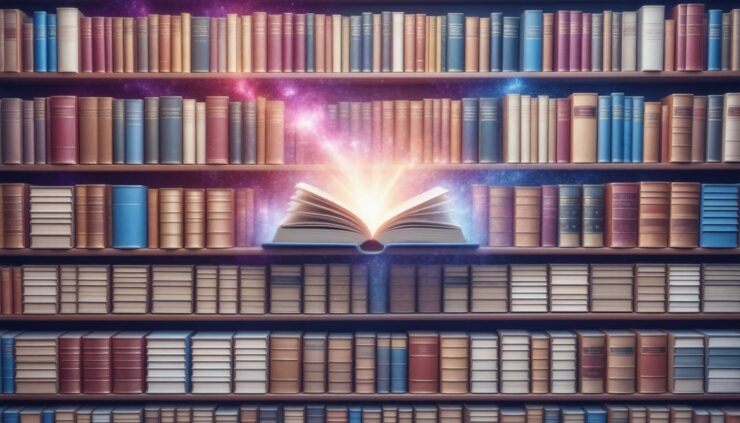歩くこと。
それはあまりにも当たり前で、つい見過ごしてしまう行為です。朝の通勤、買い物、ちょっとした散歩──私たちは日々、何気なく足を運んでいます。けれど、その「歩く」が、実は人生の深いところまで響いているとしたら……どうでしょうか。
本を読みながら、私はよく思うんです。「歩く」というのは、急がずに考えを深める知性の習慣であり、また体の不調を癒す薬であり、自然と対話する旅の入口でもあるのだと。そして時に、それは心を落ち着かせ、祈りや感謝に触れる道でもあるのです。
このRECOLLECTIONSでは、そんな「歩く」をテーマにした本を7冊、皆さんにご紹介していきます。順番は少し工夫をしました。まずは知性としての歩行を語る一冊から始め、続いて医学という裏付けを与えてくれる本へ。そして自然を味わう歩みへと広げ、技術として体を守る歩き方を学び、最後には精神を整える歩行禅にたどり着きます。
歩くことは、誰もができる行為でありながら、一人ひとりの心身に異なる響きをもたらします。本たちを通じて見えてくるのは、「歩く」が決して単なる移動手段ではなく、人生そのものを形づくる静かな革命である、ということ。
どうぞ肩の力を抜いて、この選書を読んでみてください。どの本も、明日からのあなたの一歩を、少しだけ軽くしてくれるはずです。
目次
1.知性:『歩く マジで人生が変わる習慣』(池田光史)
「歩く」──その単純な行為を、ここまで豊かに語れるのかと驚かされる一冊でした。著者・池田光史さんは、脳科学のデータから歴史的な思想家の歩行習慣までを自在に結びつけながら、「歩くことは人生を刷新する習慣である」と強調します。
たとえば、毎日の散歩が脳の海馬を刺激し、記憶や学習に関わる機能を高めるという研究。歩くだけで海馬の体積が増える、そんな結果が紹介されているのです。単なる健康法を越え、歩くことが知性の鍛錬になるという視点は新鮮でした。また、カントやダーウィンなど「歩きながら考える」ことを習慣にした偉人たちの姿も描かれます。彼らの思索は、机に座ってじっとしていたのでは生まれなかったのかもしれません。
本の中で繰り返し示されるのは、「座り続けることは喫煙に匹敵する害である」という厳しい警告。そして「会議中は歩け!」というユーモラスな提案。軽やかさと同時に、行動を促す力を秘めています。読んでいると、思わず椅子を離れて体を動かしたくなるほど。
私自身、この本を読んでから「歩くこと」を少し特別に感じるようになりました。早足で前へ進むだけでなく、歩くリズムに思考を預け、静かな時間を味わう。すると、考えが自然にほどけていく瞬間があります。歩くことは単なる運動ではなく、「知性を深める沈黙の習慣」なのだと。
本を閉じたあと、あなたも試してみませんか? スマホを置き、イヤホンを外して、ただ歩く。足音と呼吸が重なり合う時間に、きっとあなたの中の新しい答えが見えてくるはずです。
2.医学:『病気の9割は歩くだけで治る! ~歩行が人生を変える29の理由~』(長尾和宏)
「歩くだけで病気の9割は治る」──この大胆なメッセージは、多くの人に「本当に?」という驚きを与えます。けれど著者である医師・長尾和宏さんは、その言葉を医学的な裏づけと実際の臨床経験から語っています。
酸化や糖化といった老化の仕組みを抑えること。血流を促し、ホルモンバランスを整えること。さらに「DHEA」という若さを保つホルモンが歩くことで増えるという研究結果まで、本の中には科学的根拠がわかりやすく解説されています。健康を失った人が「歩く」ことをきっかけに回復していく姿も紹介されており、「お金もかからず、誰でも今から始められる」という歩行の普遍的な強みが強調されます。
私が特に心に残ったのは、歩くことが「医者に頼りきらない力」を取り戻すという視点です。診察室に入って薬を受け取るだけではなく、自分自身の足で未来の体調をつくっていく。そこには、人間の自己治癒力を信じる眼差しがあります。
歩行は運動不足の解消にとどまりません。心の不安や孤独感を和らげる効果もあると語られていました。実際に「毎日30分の散歩で不眠が改善した」「人と一緒に歩くことで会話が増えた」という事例も示され、歩くことが社会的なつながりを回復する契機になるのだと感じました。
歩き出すのに、特別な準備はいりません。靴を履いて外に出て、一歩を踏み出すだけ。けれどその一歩は、体を癒し、心を整え、人生そのものを変えていく。そんな力を信じさせてくれる本でした。
3.医学:『ヤマケイ文庫 病気の9割は歩くだけで治る! PART2』(長尾和宏)
続編であるPART2では、同じテーマをさらに具体的に深めています。前作で示された「歩行の医学的メリット」が、より多くの症例や体験談を通して展開されているのです。
印象的だったのは、「歩くことは特効薬ではないが、日常に潜む慢性的な不調を根っこから和らげる」という視点です。頭痛、肩こり、生活習慣病の予防など、どれも私たちが見過ごしがちな症状ですが、その多くが歩行の不足と結びついている。医療の現場から発せられる言葉だからこそ、説得力が強く響きます。
また本書は「知識から体感へ」という流れを促してくれる一冊でもあります。前作を読んだ読者が「実際に歩き始めたらこう変わった」という声が収められており、読むだけでなく実践することの大切さを伝えてくれます。歩行は、知識を頭に入れただけでは何も変わりません。一歩踏み出して初めて、その効能が実感となって心と体に刻まれていきます。
私はこの続編を読みながら、歩くことが「学びを現実にする橋」なのだと感じました。本を閉じて机に向かうだけでなく、靴を履いて外に出る。その行為自体が学びの完成になる──そんな稀有なテーマが「歩行」なのです。
セリナの言葉で言えば、「歩くことは、知識と実感をつなぐ静かな橋渡し」。この本は、その橋を安心して渡らせてくれる頼もしいガイドブックでした。
4.自然:『歩くを楽しむ、自然を味わう フラット登山』(佐々木俊尚)
山に登る、というと多くの人は「頂上を目指す」イメージを抱きます。けれど佐々木俊尚さんの提案する「フラット登山」は、そうした常識を静かに裏切ります。ここで語られるのは、山頂を制覇することではなく、自然のなかを気持ちよく歩くことそのものを目的にするスタイルです。
本書の特徴は、道そのものを味わう感性にあります。佐々木さんは、森の小径や湖畔の道を「官能的な山道」と呼びます。それは単に美しいというより、歩いていると五感が揺さぶられるような道。光と影のコントラスト、湿った土の匂い、鳥の声や風のざわめき──そんな要素が重なり合って、私たちを自然の物語へと招いてくれるのです。
さらに嬉しいのは、この本が具体的な30のコースガイドを紹介していること。難しい装備も必要なく、季節ごとに楽しめる身近な道が数多く紹介されています。忙しい日常の中でも、「週末に少しだけ自然に触れたい」と思ったとき、すぐに参考にできるのは大きな魅力です。
私はこの本を読みながら、「歩くことは目的地を求めなくてもいい」という気づきを得ました。山頂に立つ達成感ではなく、ただ自然のリズムに身をゆだねる。その時間は、心の奥にたまった疲れをほどき、静かな喜びを運んでくれます。
セリナとしての一言を添えるなら──「歩くことは、自然と対話する最もやさしい方法」。ゴールに追われず、ただ道に寄り添う時間は、きっとあなたの心に柔らかな余白を残してくれるでしょう。
5.技術:『腰痛、ひざ痛、足首痛、外反母趾… 痛くない!疲れない!歩き方の教科書』(木寺英史)
「歩けば歩くほど、体がつらくなる」──そんな悩みを抱えた人にとって、この本はまさに救急箱のような存在です。著者の木寺英史さんは、動作学の専門家として、正しい歩行がいかに体を守るかをわかりやすく解説しています。
本書がユニークなのは、単なる健康論ではなく「具体的な歩き方の技術書」であること。姿勢、足の着き方、腕の振り方、靴の選び方──細やかなポイントがイラストや写真とともに解説されていて、すぐに実践に移せます。特に、腰痛やひざ痛といった慢性的な不調が、誤った歩き方によって悪化しているケースを具体的に示してくれる点が印象的でした。
私が読んで心に残ったのは、「歩き方は無意識の癖が積み重なった結果」という言葉です。普段は何気なく行っている歩行も、実は自分の体に少しずつ負担をかけているかもしれません。けれど、その癖を知識で修正すれば、一歩ごとに体が軽くなり、不調は予防できる。歩き方そのものが体を守る技術になるのです。
セリナとして読者に伝えたいのは、「正しい知識は、未来を軽くする守りになる」ということ。明日からの一歩を変えるだけで、体は確実に応えてくれます。この本は、その第一歩を支えてくれる頼もしい指南書です。
6.技術:『痛み・体調不良・病気すべて解消できる超歩行』(稲村崇)
こちらの一冊は、さらに実践的なリハビリ的歩行法にフォーカスしています。タイトルにあるように、腰痛・肩こり・生活習慣病などの不調を「歩行の改善」で根本から整えることを目指しています。
特徴的なのは、「歩き直す」という発想。人は成長の過程で、いつの間にか効率的でない歩き方や悪い姿勢を身につけてしまいます。その結果、不調や痛みを招く。だからこそ、意識的に歩幅を整え、呼吸を合わせ、重心を修正し、歩行を再教育することが必要だと説きます。
具体的な方法としては、つま先の向きや骨盤の動きを意識する練習、呼吸のリズムに合わせた歩行などが紹介されています。小さな工夫の積み重ねが、からだ全体の連動性を取り戻し、自然な回復力を呼び覚ましてくれるのです。
私は読みながら、「不調は終わりではなく、新しい歩き方の始まり」という言葉が浮かびました。体がサインを出しているのは、「もう一度正しい歩き方を思い出してほしい」というメッセージなのかもしれません。
セリナの視点からいえば──「歩くことは、体に宿る記憶を更新すること」。この本は、不調に悩む人に歩き直しという優しい選択肢を差し出してくれます。痛みや疲れに囚われていた歩行が、再び自由と軽やかさを取り戻すために。
7.精神:『歩くだけで不調が消える 歩行禅のすすめ』(塩沼亮潤)
「歩くことが、そのまま心を整える修行になる」──この本を読みながら、私は静かに頷いていました。著者の塩沼亮潤さんは、千日回峰行を満行した僧侶として知られる方。その経験から語られる「歩行禅」は、単なる健康法ではなく、心のあり方を磨く道として提示されています。
歩行禅の基本は、懺悔・感謝・静寂という三つの段階にあります。行きの道では過去の自分を省みて懺悔し、帰り道では日常の恵みに感謝し、最後に坐禅で心を鎮める。歩くというシンプルな動作に、祈りと気づきを重ねていくのです。その流れは、まるで呼吸を深めるように、自然に心を浄化していきます。
読者の体験談も印象的でした。「不眠が改善した」「心のざわめきが落ち着いた」「腰痛や気分の落ち込みが和らいだ」といった声が寄せられており、歩くことが身体の不調だけでなく、心の痛みも和らげていくことが伝わってきます。医学や科学の言葉では表しきれない静かな効能が、ここにはあるのだと思いました。
私はこの本を通じて、「歩くことは心に問いを投げかける時間」だと感じました。ひとりで歩いていると、不思議と答えを出そうとしなくても、問いの輪郭が浮かび上がってきます。セリナの言葉でいえば、「歩みの中に祈りを見つける」ということ。足を運ぶたびに、心の奥にある感情や願いが、少しずつ整っていくのです。
もし日々の忙しさや不安に追われているなら、一度「歩行禅」を試してみてほしい。深い静寂の中で歩く時間は、きっとあなたに生きることのやさしさを思い出させてくれるでしょう。
🔶 結び

ここまで七冊の本をめぐりながら、「歩く」という行為の多面性を見てきました。知性を磨く習慣としての歩行。医学的な裏づけに支えられた、体を癒す薬としての歩行。自然の中で心を解き放ち、ただ道そのものを楽しむ歩行。正しい技術を学ぶことで、未来の体を守る歩行。そして、祈りや感謝を伴って心を鎮める歩行。──それぞれが違う顔を持ちながら、すべて「歩く」という同じ行為の中に重なり合っているのです。
私たちは日常の中で、移動のために歩き、運動不足を補うために歩きます。でも本を通して見えてきたのは、それだけではありません。歩くことは自分の内側と外側をつなぐ橋であり、心身の調和を取り戻す最も身近な術なのだということ。
そして何より、歩くことは誰にでもできる──ここに大きな希望があります。特別な道具もいらず、今この瞬間から始められる。たとえ一分でも、数歩でも、それは未来への小さな投資です。
セリナとして最後に伝えたいのは、「急がず、でも止まらず」ということ。早く結果を出そうと焦る必要はありません。ただ一歩を重ねていくうちに、体は軽くなり、心は整い、思考は深まり、あなたの歩みはやがて人生を優しく変えていくはずです。
今日の一歩が、明日のあなたを形づくる。どうかこの本たちを手に取り、あなた自身の歩き方を見つけてください。その歩みの先に広がる景色は、きっと今よりも澄んで、やわらかく、あなたを迎えてくれるでしょう。